ドラマ「光る君へ」をご覧になった方は、
まひろが琵琶を弾く姿に魅了されたことでしょう。
彼女の演奏は非常に滑らかで、
まるで誰にでも簡単に弾けるように見えます。
本当に簡単そうですよね。
しかし、この見た目のシンプルさには多くの技術と経験が隠されていて、
まひろ:吉高由里子さんは左利きを右利きに直して、
練習に励んだそうです。
”琵琶”は本当に難しい楽器なのか?調べてみました。
琵琶の基本構造と演奏方法
琵琶は、日本の伝統楽器の一つで、
撥(ばち)という大きなピックを使って弦を弾くことが特徴です。
琵琶には4弦や5弦のものがあり、
基本的な演奏方法としては、
撥で弦を弾きながら左手で音程を調整します。
この一見単純な動作にも、
多くのテクニックと練習が必要です。
琵琶演奏の難しさ
琵琶の演奏が難しいとされる理由は以下の通りです。
- 正確な指の位置:左手で弦を押さえる位置が非常に重要で、音程を正確に取るためには高度な指使いが求められます。
- 撥の使い方:撥を使って弦を弾く際の角度や力加減も非常に繊細で、適切に音を出すためには長い練習が必要です。
- リズム感と表現力:琵琶はリズム感と表現力が重視される楽器であり、単に音を出すだけでなく、感情豊かに演奏するためには深い理解と技術が必要です。
まひろの演奏が簡単に見える理由
まひろが琵琶を演奏する姿が簡単に見えるのは、
彼女の演奏技術が非常に高いからです。
熟練した演奏者は、
難しい技術を自然に見せることができ、
見る者に「簡単そう」と感じさせることがあります。
これは彼女の地道な練習と努力によるものです。
琵琶を始めるためのステップ
もしあなたが琵琶に興味を持ったなら、
以下のステップで始めてみると良いでしょう。
- 楽器の購入またはレンタル:初心者向けの琵琶を手に入れることから始めましょう。
- 基本的な練習:撥の持ち方や弦の押さえ方、基本的な音階練習を行います。
- レッスンの受講:琵琶の専門家からの指導を受けることで、効率的に技術を習得できます。
- 練習の継続:毎日の練習が上達の鍵です。短期間での上達は難しいですが、継続的な努力が実を結びます。
琵琶と楽器について
琵琶の歴史は古く、中国、ベトナム、日本など各地に伝えられて、
それぞれ発達してきました。
種類
日本には琵琶が5種類も存在します。
①楽琵琶
雅楽(日本の古典音楽の1つ)のうち管絃(楽器のみの演奏)と催馬楽(平安時代にできた歌曲の1つ)を演奏する時に用いられる琵琶です。
日本初の琵琶として知られ、雅楽の中ではリズム楽器として分散和音を奏でるのが特徴的と言えるでしょう。
②平家琵琶
鎌倉時代から読み継がれる軍記物の名作「平家物語」に節をつけて歌いながら演奏する時に用いられる琵琶です。
この演奏様式を「平曲」と言いますが、現在でも数々の演奏会が開かれています。
③盲僧琵琶
盲目の琵琶奏者である琵琶法師、琵琶法師が奏でた琵琶、琵琶法師が演奏した宗教音楽のことを指します。
楽器としての盲僧琵琶は荒神経、地神経などのお経を唱える時の伴奏として用いられました。
④薩摩琵琶
室町時代に武士の教養のための音楽として生まれ、武士たちの士気向上のため勇壮で大きな音が出るように楽器や撥が改良されていったのです。
武士道や儒教、仏教の教えなどが取り入れられ、西南戦争などの戦いのさなかにも演奏されたと伝えられています。
⑤筑前琵琶
宗教性を脱して明治時代に女性を対象とする家庭音楽として確立しました。
歌と演奏が一体化し調絃なども三味線に準ずるようになったのが特徴的と言えるでしょう。
価格
琵琶という楽器の価格相場は和楽器の中でもかなり高価格と言えます。
新品であれば80万円~130万円、初心者用の普及品でも40万円ほどになります。
これならばギターとかのほうが手軽でいいかもしれないですね。
オークションなどにも出品されていることがありますが、
壊れていたり、ジャンク品だったりという可能性もあるので気をつけましょう。
まひろの演奏に感銘を受けた方は多いでしょう。
その見た目の簡単さに惑わされず、
琵琶の奥深さと難しさを理解することで、
さらにその演奏の素晴らしさを感じることができるでしょう。
琵琶の魅力に触れ、
ぜひその美しい音色を自らの手で奏でてみてください。
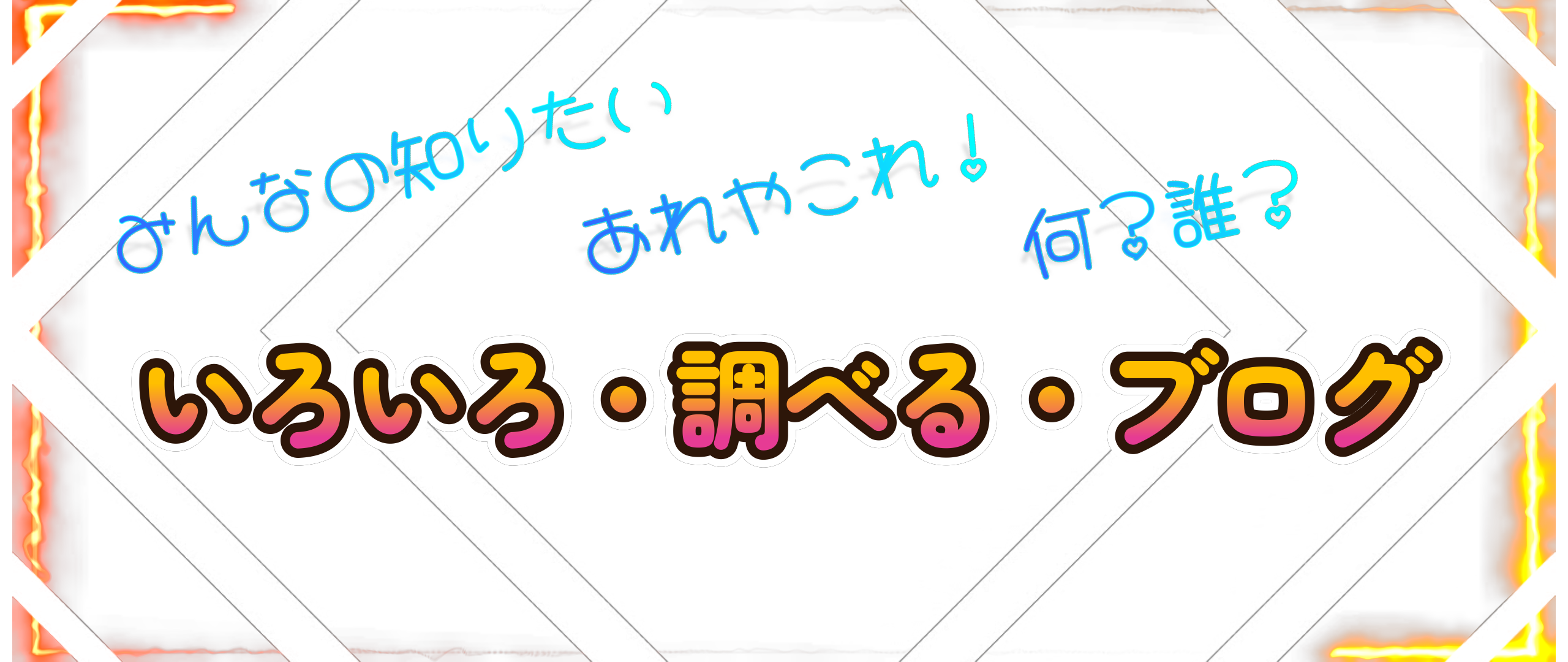
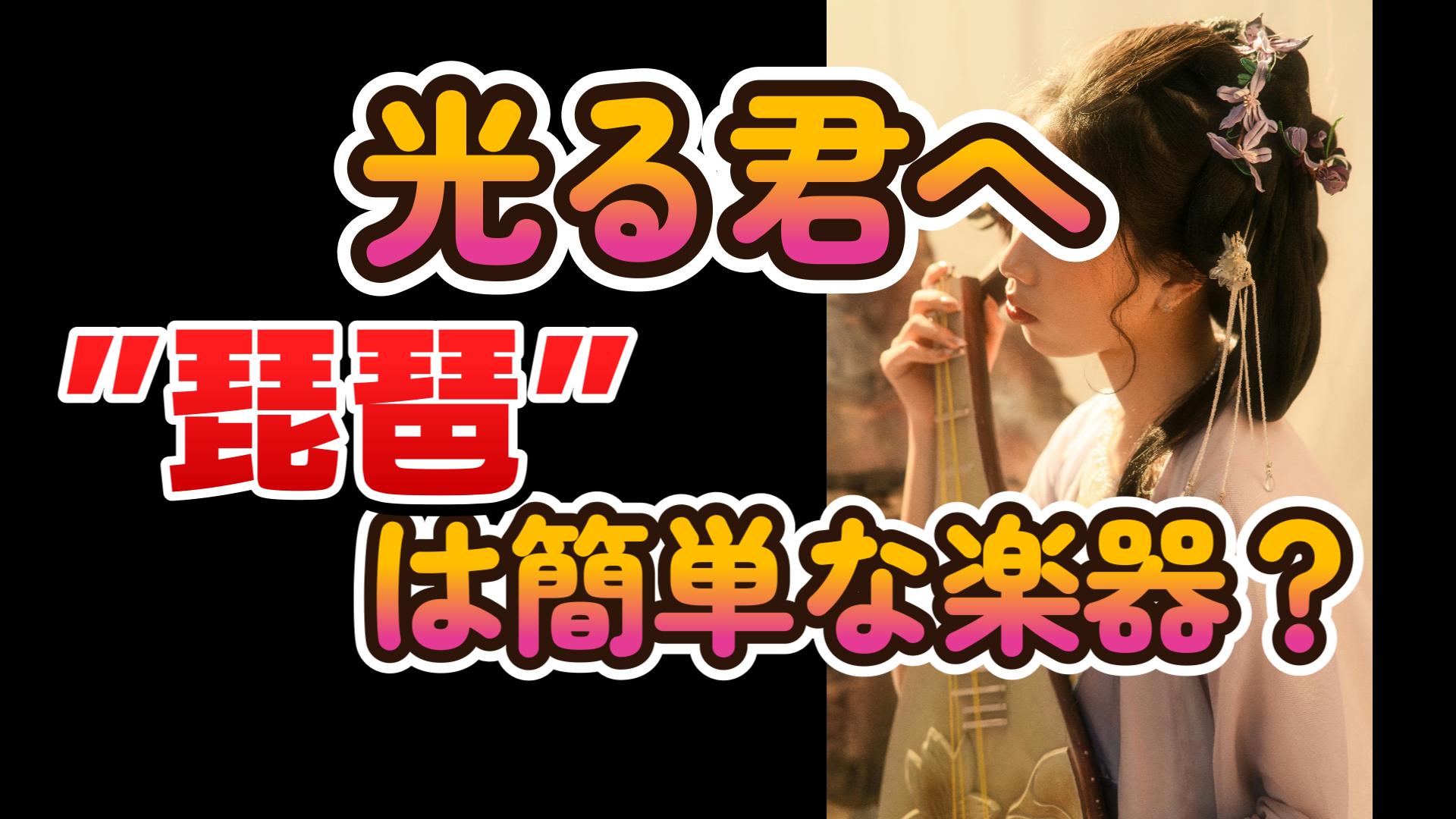


コメント