現在、将棋界では藤井聡太さんが8つのタイトルを、
すべて独占しています。
この将棋のタイトルはどのような歴史と特色があるか?
由来を知らべてみました。
1. 竜王戦(りゅうおうせん)
竜王戦は、
将棋のタイトル戦の中でも最高峰とされるタイトルです。
1988年に創設され、
日本将棋連盟と読売新聞社が主催しています。
プロ棋士たちは予選を経て本戦トーナメントを戦い抜き、
最終的には挑戦者決定三番勝負を制した者が、
現竜王との七番勝負に挑みます。
勝者が竜王のタイトルを手にし、
その栄誉とともに賞金も非常に高額で、
竜王戦の優勝賞金は将棋界最高の4400万円で、
持ち時間はそれぞれ8時間となっています。
永世称号である「永世竜王」は、
竜王を連続5期もしくは通算7期以上保持した棋士に与えられる。
2. 名人戦(めいじんせん)
名人戦は、
将棋界で最も歴史のあるタイトル戦です。
1935年に創設され、
毎日新聞社と朝日新聞社および日本将棋連盟が主催しています。
名人戦の挑戦者は、
順位戦という年間を通じて行われるリーグ戦で最上位に立った者が挑む形式です。
名人のタイトルは長年にわたり将棋界の頂点とされており、
その格式と伝統は他のタイトルを凌駕します。
持ち時間は2日制の各9時間で、
これは将棋の全タイトル戦のうち最長時間である。
1日目の終わりには封じ手を行い、
2日目の開始まで次の手を考えて有利になることがないようにする。
名人位を通算5期以上獲得した棋士は、
原則として引退後に、永世称号である「永世名人」を名乗ることができる。
他のタイトルの永世称号と異なり、
「○世名人」という称号となる。
これは、江戸時代から続く終世名人制を引き継ぐためである。
賞金は推定で3000万~3500万
3. 叡王戦(えいおうせん)
叡王戦は、
比較的新しいタイトル戦で2015年に創設されました。
日本将棋連盟とドワンゴが主催しています。
予選を勝ち抜いた棋士が本戦トーナメントで戦い、
最終的に挑戦者決定戦を制した者が、
現叡王との七番勝負に挑みます。
本棋戦発足以前、
プロ棋士対コンピュータ将棋ソフトウェアの棋戦である
将棋電王戦が開催されていたが、
2015年の電王戦FINALをもって団体戦としての電王戦は一つの区切りとされた。
電王戦に類する棋戦の存続を希望したドワンゴが日本将棋連盟と協議した結果、
まずドワンゴ主催で新たな一般棋戦を立ち上げ、
優勝者が、電王トーナメントを勝ちあがったコンピュータ将棋ソフトウェアと、
装いを新たにした電王戦で対局する事で合意した。
新棋戦の名称は一般公募から選出され、
公募案から主催者が9つに絞り込んだ上で、
公式サイトから一般投票を行い、
「叡王戦」に決定。優勝者は「叡王」の称号を得る。
対局の模様をネット配信を通じて幅広い視聴者層にアピールしている点が特徴です。
持ち時間は1人1時間の場合もあり(5時間、6時間などもある変則制)
名人戦と違い1日で決着がつきます。
永世称号である「永世叡王」は、
叡王を通算5期以上保持した棋士に与えられる。
賞金は推定で1,600~2,000万円
4. 王位戦(おういせん)
王位戦は、
新聞3社連合(北海道新聞社、中日新聞社、神戸新聞社、徳島新聞社、西日本新聞社)
及び日本将棋連盟が主催するタイトル戦です。
2021年、緑茶飲料「お〜いお茶」を製造販売している伊藤園が特別協賛を発表。
第64期以降は協賛企業と商品名を冠した「伊藤園お〜いお茶杯王位戦」となっている。
予選を勝ち抜いた棋士がリーグ戦に進み、
そこで勝ち抜いた者が挑戦者決定戦を経て現王位との七番勝負に挑みます。
長丁場のリーグ戦を勝ち抜く必要があり、
その勝者には高い実力が要求されます。
持ち時間は予選・挑戦者決定リーグ・挑戦者決定戦が各4時間。
七番勝負は持ち時間8時間の2日制で、
1日目の終わりには封じ手を行う。
永世称号である「永世王位」は、
王位を通算10期もしくは連続5期以上保持した棋士に与えられる。
賞金は推定で800~1,200万円
5. 王座戦(おうざせん)
王座戦は、
1953年に創設されたタイトル戦で、
日本経済新聞社及び日本将棋連盟が主催しています。
予選を勝ち抜いた棋士が本戦トーナメントで戦い、
最終的に挑戦者決定戦を経て現王座との五番勝負に挑みます。
毎年秋に行われる五番勝負は、
将棋ファンにとっての大きな注目イベントです。
王座と挑戦者がタイトルをかけて戦う五番勝負は、
全国各地のホテルや旅館、料亭などで実施されます。
休憩時間については、昼食休憩と夕食休憩があり、
その時に棋士が食べる昼飯やおやつに注目があつまります。
なお、8つのタイトル戦の番勝負において夕食休憩があるのは、
名人戦(2日目)と王座戦の2棋戦のみである。
永世称号である「名誉王座」は、
王座を連続5期もしくは通算10期以上保持した棋士に与えられる。
将棋界で8大タイトルの永世称号として「永世」ではなく「名誉」を冠するのは、
王座戦だけである。
賞金は推定で700~1,100万円
6. 棋王戦(きおうせん)
棋王戦は、
1974年に創設されたタイトル戦で、
共同通信社および日本将棋連盟が主催しています。
予選を勝ち抜いた棋士が本戦トーナメントで戦い、
最終的に挑戦者決定戦を経て現棋王との五番勝負に挑みます。
2021年、コナミグループが特別協賛、大塚製薬が協賛を発表。
これにより、第48期からは棋戦表記が「棋王戦コナミグループ杯」となる。
棋王戦は、実力を示す場としての重要性が高く、
特に若手棋士にとっては登竜門となっています。
永世称号である「永世棋王」の資格は、
棋王位を連続5期以上保持した棋士に与えられる。
現在、将棋界のタイトルで通算期数で永世位を獲得できないのは棋王のみである。
賞金は推定で600~1,000万円
7. 王将戦(おうしょうせん)
王将戦は、
1951年に創設されたタイトル戦で、
スポーツニッポン新聞社と毎日新聞社および日本将棋連盟が主催しています。
予選を勝ち抜いた棋士がリーグ戦に進み、
そこで勝ち抜いた者が挑戦者決定戦を経て現王将との七番勝負に挑みます。
王将戦は、持ち時間が長く、
深い読みが求められる点が特徴です。
棋戦名は駒の「王将」が由来になっています。
2019年度の第69期において外食チェーン「大阪王将」を運営している
イートアンドが特別協賛に加わり、
現在は正式名称を「大阪王将杯王将戦」として行われている。
永世称号である「永世王将」は、
王将のタイトルを通算10期以上保持した棋士に与えられる。
賞金は推定で500~800万円
8. 棋聖戦(きせいせん)
棋聖戦は、
1962年に創設されたタイトル戦で、
産経新聞社及び日本将棋連盟が主催しています。
予選を勝ち抜いた棋士が本戦トーナメントで戦い、
最終的に挑戦者決定戦を経て現棋聖との五番勝負に挑みます。
棋聖戦は、
他のタイトル戦と比べて挑戦者決定のためのトーナメントがシンプルであり、
迅速な進行が特徴です。
タイトル名の「棋聖」は、
本来は将棋・囲碁に抜群の才能を示す者への尊称であった。
将棋では特に江戸時代末期に現れた、
天野には十三世名人の関根金次郎によって棋聖の称号が贈られている。
永世称号である「永世棋聖」は、棋聖位を通算5期以上保持した棋士に与えられる。
賞金は推定で300~700万円
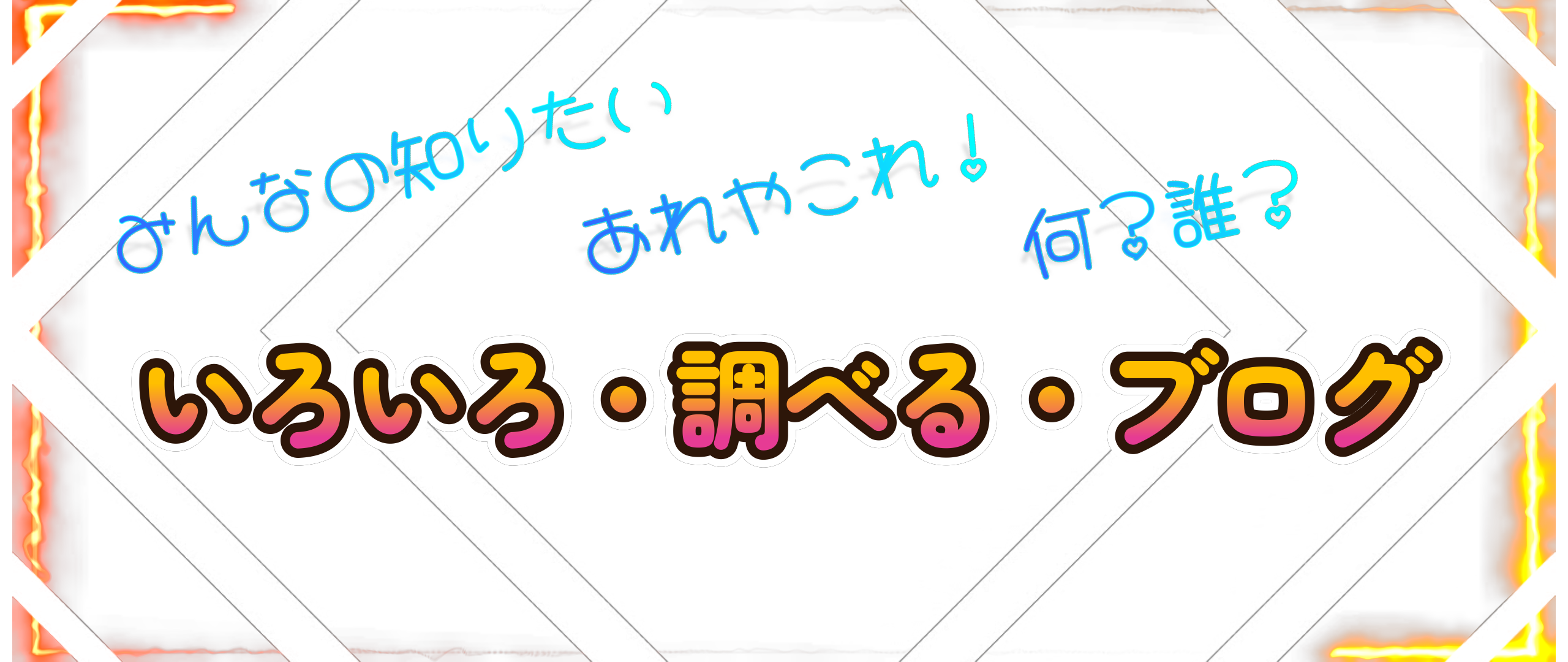
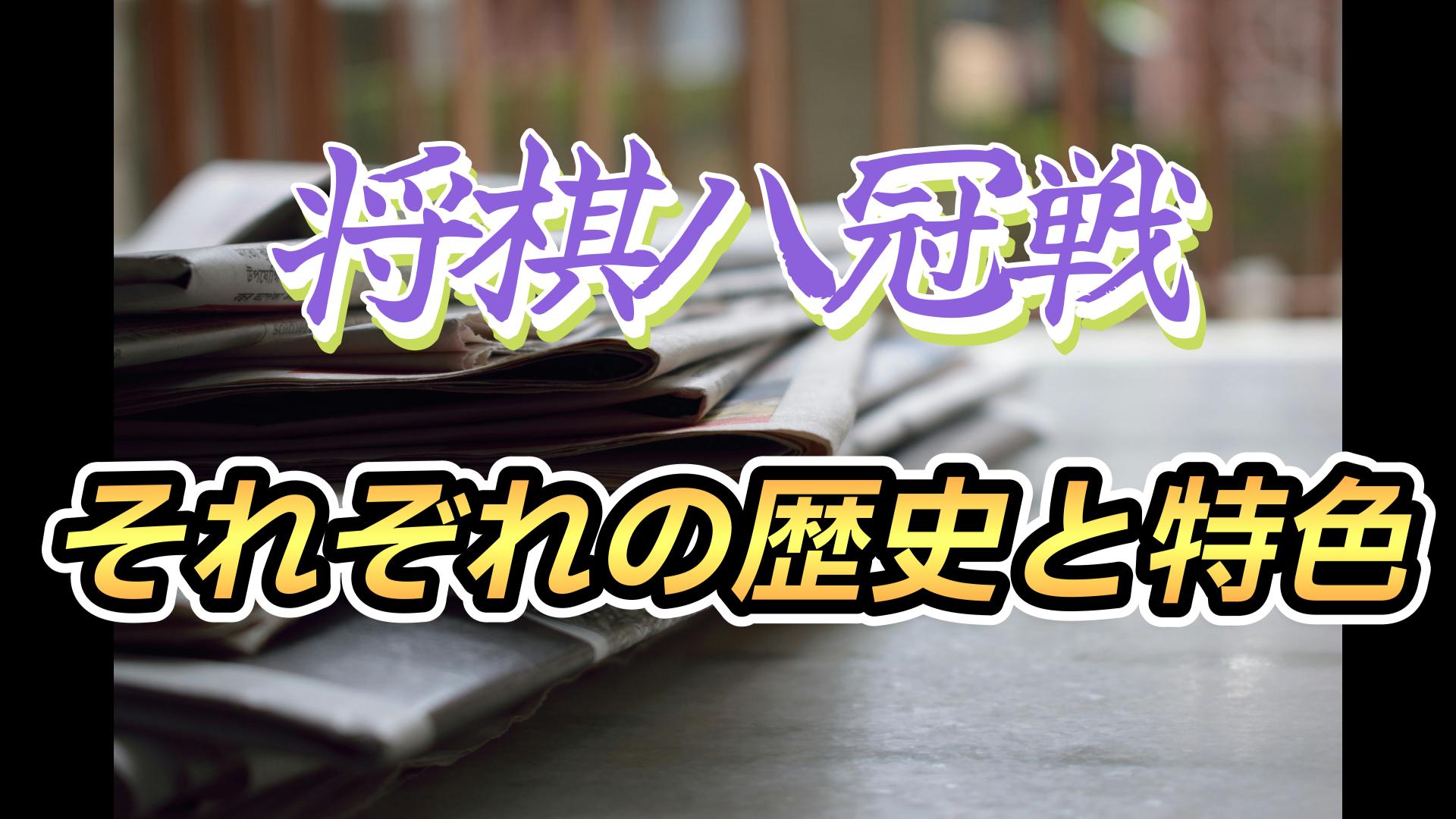


コメント